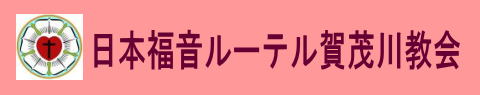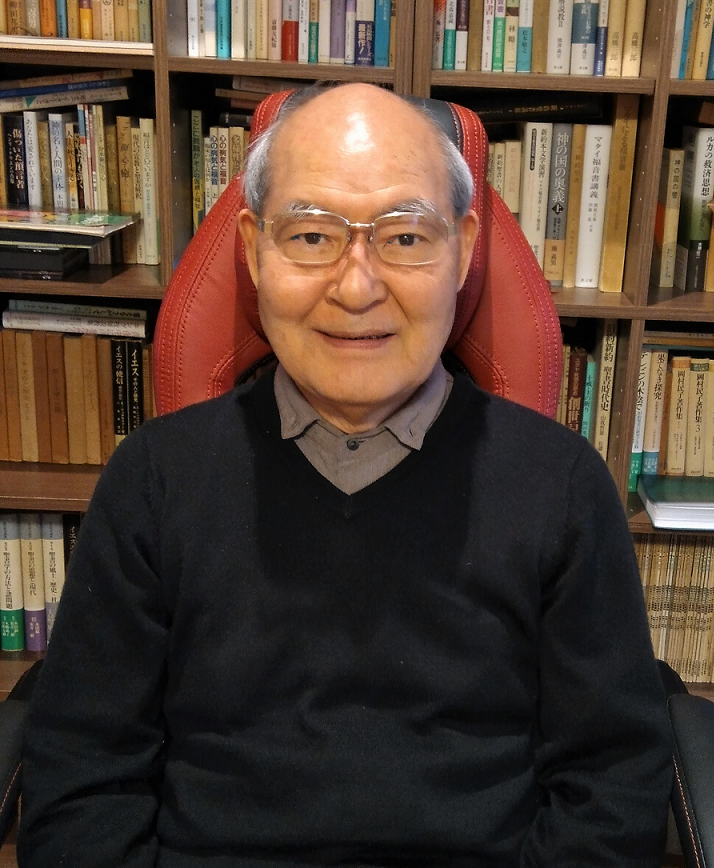2023年 牧師メッセージpastor'S message
「隣人への愛の力はどこから?」Ⅲ
大宮 陸孝 牧師
「イエスはわたしたちのために、命を捨ててくださいました。そのことによって、わたしたちは愛を知りました。だから、わたしたちも兄弟のために命を捨てるべきです。」
Ⅰヨハネの手紙3章16節
新しい年を迎えました。子供たちにとっては年度最後の学期です。昨年の秋頃から、全国各地の住宅地にクマが出没し、人に危害を与える事件が相次いでいます。「一戸建て 手が出る土地は クマも出る」との川柳がありました。世界のあちこちで戦争が多発し、自然災害も拡大する一方です。人も動物も大変な時代を迎えて、苦しみが増大しています。バーンアウトシンドロームなどと言っていられない厳しい現実とどう向き合って行くのかを考えさせられます。
この三学期には教会歴では、キリストの顕現を覚える時から受難節へと移行して行きます。キリストがいろいろな試練を受けてお苦しみになられたこと、そして、十字架につけられて、痛ましい死を遂げられたことを覚える期間を過ごします。
余りにも純粋で献身的な「愛と真実」に生きられたキリストは、かえってユダヤ教の指導者階級に疎んじられ、信頼していた弟子たちにも裏切られ、見捨てられるという悲痛な体験をなさいます。自業自得でそうなったのではありません。それもこれも私たち人間の自己中心による罪のゆえでした。神に従わない、エゴイストである人間、その罪を一身に引き受けられ、人間に変わってその結果を負われて、さらに、罪深い私たちのために祈ってくださっている。これがキリストの「苦しみ」の意味です。
十字架の苦しい息の下で祈られた祈りがあります。「父よ(神よ)彼らをお赦しください。自分が何をしているのか知らないのです」(ルカ福音書23:34)この十字架上の苦しみと祈り、そこからこんこんと溢れ流れて来るのは、キリストの私たちへの激烈な愛です。このお苦しみの意味をわかろうとせず、無知で反抗ばかりしている自分勝手な私。この自分のためにも執り成しておられる愛と慈しみが、溢れるばかり私の心に注がれているのです。主の苦しみはそこに大切な意味がある、測り知れない神の深い愛と慈しみが、あの苦しみに宿されているのです。
そしてこの十字架に示された神の愛、キリストの愛に新しい命の力をいただいてあなた方も互いに愛し合うようにと勧告されます。
「わたしがあなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これがわたしの掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない」(ヨハネ15:12~13)
私たちはこの世界の人間の罪の苦しみから逃れる道はありません。「生」と「苦」、それは実に生きることの表裏一体の関係なのです。しかし、その苦しみは意味の無い苦しみであろうか。神の愛に生きる者は、この神からの新しい創造のエネルギーをいただいて、この世の苦しみに燃え尽きることなく耐え、新しい命の実を結ぶのです。キリストの愛の御手にしっかり繋がっていることが大切です。そうすると不毛な大地と思われる私たちの現実の中で知らない間に愛の実が結ぶのです。
「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできないからである」(ヨハネ15:5)
教会とキリストというぶどうの木に、枝となって結びついているならば、この幹から溢れてくる神の命の水に養われて、愛の実が結ばれるのです。汲めども尽きない命の源、キリストという幹につながっている所には、思いを超えた実が結ぶのです。お互いを思いやる心、忍耐強く、燃え尽きず仕え合う心が育って行くのです。
2024年1月4日
「隣人への愛の力はどこから?」Ⅱ
大宮 陸孝 牧師
「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい」
ルカによる福音書10章27節
私は現在77歳、早生まれで来年一月に誕生日を迎えて78歳になります。毎年欠かさず健康診断を受ける。毎日散歩をするなどして体を動かす。野菜中心の食生活を心がける。等々ライフサイクルを健康に生きるための課題が増大しています。と同時に少しずつ以前には一人でたやすく出来たことが、体力や体の衰えなどで少しずつ出来なくなってきていることをも感じます。庭木の手入れや日除けをつけたり外したり、家の中の高い棚の上のものを下ろしたり、エアコンの掃除をするなどの作業のために、脚立に昇ることがこんなに大変なことだとは以前には思っても見なかったことでした。危ないと思ったら素早くぴょんと飛び降りるだけのことが今は出来なくなっています。そして、2段目の踏ざんと3段目の踏ざんの間が丁度よい具合になるように調節できているか、ロック金具が確実にロックされているか、梯子を背にして上り降りをしない、梯子から身を乗り出して作業をしない、身体が安定を得られないような荷物を持って上り降りをしないなど脚立や梯子の安全な使い方をより慎重に心がけなければならなくなってきています。そして、さらに梯子を支える補助者が必要になってきています。以前には一人で易々と出来たことが二人がかりでやっとできるという状態です。
子どもの成長をサポートして行くのもこれと似ていて、周囲の働きかけによって一人では出来ない課題を遂行できるようになるとの考えから、周囲がどのようにサポートしていくかに関する理論として、足場かけ理論が提唱されています。足場と言えば上記しましたように、建築現場などで作業員の作業をサポートするために一時的に設置されるもので、建物が建設されると撤去されるものです。子どもの成長も同じことで、ひとつ上のステップに行けるサポート(足場)を周囲が与え、その子どもが自立できるようになれば、次第に足場を外していくという支援のプロセスを辿ることを言います。(この意味ではお年寄りのサポートとはその方向性は正反対になります。)
自分の力で易々と解ける問題をたくさん解く学習と、一人では解くのが難しい問題を教師が助言を与えながら1問解くのと、どちらが効果的かと言うと、発達の最近接領域の考え方に基づけば、教師が助言を与えながら難しい問題を1問解く方が効果が高いと考えられます。そして、一人では解けなかった問題を教師からの助言を得て解くうちに、次第に助言がなくても自分の力で解けるようになって行き、学力が身について行くということです。
たとえば、保育園児で逆上がりを練習している子どもがいて足の蹴上がりはできるけど、腰の回転がうまく出来ていない子どもがいるとします。大人が子どもの腰に手を添えて、蹴上がりと同時に腰の回し方のコツを身につけさせることで、逆上がりを出来るように指導していくということが考えられます。こうして、大人のサポートによって達成可能な水準が発達の最近接領域ということなのです。
そこで大切なのは、できないことの中からサポートがあればできるようになるかもしれないことを抽出し、それに対して適切なサポートを与えるということです。船頭多くして船山に昇る式の過干渉、やり過ぎるのもよくありませんし、かといって、放任し過ぎるのもいつまで経っても上のステップに辿りつかないということが懸念されます。一人では出来ないけれども、周囲のサポートがあればできるようになるという最近接領域が成長・発達を促す上で効果的であるのですが、そこで重要となるのが、発達の最近接領域を見極めることです。どこまで一人で遂行でき、誰かの協力があれば達成できる領域はどこまでなのか、子どもの現状を正しく把握することが必要となります。大人と子どもが向き合いコミュニケーションを取りながら発達の最近接領域を捉え、周囲が適切なサポートを与えることで、はじめて子どもは自分自身の可能性を広げて行き、成長・発達を遂げて行くようになることが期待できるのです。そしてそのようにサポートをしてもらう経験によって、さらに子ども自身が主体的に他者との人間関係を豊かに築いてゆく大人へと成長して行くことにも繋がるのではなかろうかとも思います。
2023年12月1日
「隣人への愛の力はどこから?」Ⅰ
大宮 陸孝 牧師
「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい」 ルカによる福音書10章27節
いろいろな友だちと遊ばせようとしても、現代は遊ぶ仲間がいない、遊ぶ場所がない、遊ぶ時間がないとよく言われます。だからといって、時間を与えて場所を与えて仲間を与えてみても、それで遊べるかというと、それでも遊べないのが現代っ子だと言われます。ちゃんと遊べるようになるには、一定のサポートが必要になっているのが現代っ子の特徴のようです。
十年ほど前になりますが、フインランドに研修旅行に行きましたときに、放課後に子どもたちはどのように過ごしているのかを尋ねましたら、地域毎に子どもたちが集まる公園や遊び場に児童館のような施設が設置され、国家資格を持つ教師が(公務員として)その施設に配置されていて、集まって来る子どもたちをカリキュラムを作成して指導しているのだそうです。なるほど、塾もないのに子どもの学力が高い(十数年ほど前には世界第一位の時もありました)理由はそういうことであったかと納得したことでした。
遊ぶ場所、仲間、時間が与えられても遊べない理由、それは想像力と創造力が欠けている、育っていないからだと考えられます。ヴィゴツキーは言います。「こどもは竹箒に乗っていても馬に乗っている、手を広げればトンボになっている、ある空間が掘っ立て小屋にも、お城にもなる、ある空間が、ある物体が、ある人物が子どもの想像の中で何にでも変化する。子どもはそういう想像力を持っている」と。がしかし、今の子どもたちにはそのような想像力が発達していないということです。
ひどいいじめをするのは、相手の悲しみを想像する力が無いからで、同時に、相手の悲しみや痛みを思いやれるのは、自分の生活の中で、自分の悲しみを両親や祖父母、あるいは周囲の人たちに充分思いやられてきたという生い立ちがかかわってくるのです。自分が思いやられる前に自分が相手を思いやれることは、子どもには決してないのです。思いやられた子が人を思いやることができる。同時に遊びの中で想像力・創造力を豊かに育ててきた子どもが、他者の苦しみや悲しみを想像することができるということです。
ヴィゴツキーはそのように遊びの意味と人格形成に及ぼす本当の意味を研究した人物です。「僕の先生は学校の先生じゃない。僕の先生は山と川なんだ」と言ったのは「釣りキチ三平」を書いた漫画家矢口高雄ですが、そのように自然の中で創造力・想像力を働かせて思いっきり遊ぶ中で、善も悪もみんな仕入れて、いろいろな能力や個性や資質を身につけて行って総合的な人間形成・人格形成をし、そしてそれを応用する能力、つまり将来の社会性、働くことあるいは人と関わる力として身につけていくのだということでしょう。わたしたち自身にもそういうふうに育てられた人格形成のプロセスが沈んでいるのだし、私もそうなのだということです。
要するにビヴィゴツキーは、自分一人で出来ることばかりに取り組んでいても効果的な成長や発達は望めない、自力ではむずかしいが、誰かのサポートがあれば出来るようになることの領域を、「発達の最近接領域」としてその領域に取り組むことが成長・発達を促す上で重要であると提唱しているのです。今の時点で自力で課題を解決できる、現下の発達水準に対して、他者の助けを借りれば解決できる水準の差、つまり、既に一人で出来ることと、まだできないことの間にある、一人では出来ないけど、外部の助けがあればできる領域のことを指し、この領域での学習が効果的な成長・発達を促すとされます。
ヴィゴツキーは、子どもは他者との関わりを通じて発達を遂げるとして、出来るようになるまで発達を待つのではなく、発達の最近接領域に対して働きかけることが重要であると提言しています。具体的には、現時点で解決できる内容よりも多少難しい課題を与えた上で、助言を与えたり、自分より高い発達水準にある仲間と共同して取り組ませたりすることで課題を達成させるプロセスを踏むことになります。そこでさらに重要になってくるのが、子どもの解決を促すサポートをどのようにして行くかということです。そのようなサポート理論として「足場かけ」という理論が提唱されています。 以下次号
2023年11月1日
「集中して取り組むことの重要性Ⅱ」
大宮 陸孝 牧師
「わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。・・・わたしは、神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおの、どのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれも他の土台を据えることはできません。」
(第一コリントの信徒への手紙3章6節~7節、10節~11節)
今年の中秋の名月は9月29日でした。今年は暑い日が長期に亘って続いておりましたが、10月になり、日に日に空気が秋めいて、空が澄んで月をくっきりと夜空に映し出す季節となって行きます。中秋とは、旧暦の8月15日を指し、旧暦の7月から9月を秋としているため、8月15日は丁度秋の真ん中となり、その頃は1年を通して月が最も美しく見える時期であるとされ、平安時代の貴族たちは中秋の名月に月を眺めて和歌を詠む「観月の宴」を開いて楽しんだということです。中秋の名月は現在では新暦の9月下旬から10月となり、丁度今頃のこの時期のこと、風が心地よく虫の鳴き声が聞こえはじめるのももうそろそろです。今年待ちに待った秋の季節がようやくやって来きます。
さて、前回発達心理学者ヴィゴツキーについて話しをすると予告を致しました。ヴィゴツキーはロシア(旧ソ連)の心理学者であり、心理学のモーツァルトとも呼ばれる天才と称された優れた心理学者でありました。心理学者としての活動期間は10年ほどで、38歳で亡くなるまでに数多くの発達理論を提唱しています。その中でも特に人との関わり、つまり、社会的相互作用に注目した発達理論は傑出していて、高く評価されています。
コミュニケーションというのは話し手と聞き手という2つの役割があり、それぞれは役割を交代しながら相互に影響を与え合うものです。そしてそのような社会的な関わりを通じて、発達に必要な情報が提供され、それが個人の中に取り入れられる(内化される)ことで新しい認識の形成が促進されると言う理論を提唱しました。そして、発達に於いて重要なコミュニケーションを行う相手は、同年齢の仲間だけではなく、大人や、より発達の進んだ年長者も含まれていて、幅広い他者との関わりを通じて子どもは認知的な発達を遂げるとされます。人間の発達は自動的に進むものではなく、教育的な働きかけに対して、子どもが積極的にそれを取り入れようとする、ヴィゴツキーはそのことを内化と呼び、子どもはそれを積極的に行っていると主張したのです。
ヴィゴツキーは子どもの発達に於いて重要となる社会的な関わり、コミュニケーションの重要性を強調していますが、そこで使用される言語にも注目しています。子どもの言語の発達を考える上で重要となってくる概念に内言と外言というものがあります。外言は音声として発せられる言葉のことで、コミュニケーションの道具として用いられる言語のことです。内言とは思考の道具として用いられ、音声化されない言語のことです。外言は私たちが普段、人と対話をする際に用いている言語のことですが、実は内言も私たちに欠かせない言語です。私たちは普段の生活の中で、口には出さないけれども頭の中で言語を使って思考をまとめたり、自分に言い聞かせたりする作業をしています。内言は私たちの思考や自己調整に大きく関わっている大変重要な言語なのです。
そして、ヴィゴツキーは人間の認知発達を促進する内化と関わるものとして発達の最近接領域を提唱しました。次回はこれを取り上げてお話しさせていただきます。
2023年10月1日
「集中して取り組むことの重要性Ⅰ」
大宮 陸孝 牧師
「わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。・・・わたしは、神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおの、どのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストという既に据えられている土台を無視して、だれも他の土台を据えることはできません。」
(第一コリントの信徒への手紙3章6節~7節、10節~11節)
9月になってもまだ暑い夏日が続いています。間もなくやって来る秋の季節が待ち遠しく感じるこのごろです。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、観光の秋、実りの秋、文化活動の秋、天高く馬肥ゆる秋等々、命の躍動・成長の季節を迎えようとしています。
第71期将棋王座戦五番勝負は史上3人目となる名誉王座がかかる永瀬拓矢王座と、前人未踏の八冠独占を目指す藤井聡太七冠の歴史的な対決が始まりました。藤井七冠は5歳で祖母に教えられて将棋を始め、小学3年生で全国大会優勝という目覚ましい成長を遂げ、中学2年生14歳2ヶ月でプロ棋士の仲間入り、15歳で公式戦29連勝新記録を達成し、17歳で棋聖のタイトルを獲得、今年度には21歳にして名人を含めて七冠獲得を史上最年少で果たしました。私たちはこの7年の間藤井七冠の驚くべき集中力を目の当たりにして来たのでした。
藤井七冠は8月24日の会見で王座戦に向けて『八冠挑戦は光栄だが、まだ足りないところが多い。しっかり集中して臨みたい』と気を引き締めていました。人間の成長にとって重要なことは集中力であるということを改めて知らされます。
「子どもの遊びは子どもにとって仕事だ」などと言われます。子どもの遊びがもたらす意味とは何か?それは暇つぶしではありません。また、ただ面白いことを求めたり、ストレス解消をしているのでもありません。子どもの遊びの意味と遊び方と、それが人格形成に及ぼす本当の意味は、遊びそのものが直接的に生産性と創造性を持っているということだと言うことを私たちは認識しなければなりません。子どもは単純におもしろいことを求めて遊んでいるのではなく、よくよく観察しますと、遊びの中で苦しみを自ら積極的に背負おうとします。なぜ子どもは遊びの中で苦しいことを背負い、困難に挑戦しようとするのか、それは発達・成長という衝動があるからだ、ということです。
子どもの遊びをずっと見ていると、昨日と同じことはしていない、昨日より上手になろうとしている。昨日よりも発展しようとしている極端に言いますと、さっきよりも発展しようとしている、二度と同じことをしていないということです。絶えず一歩次の段階に踏み出そうとしているということです。木登りをすれば昨日よりも高く昇りたい、上手に昇りたい、竹馬をすれば昨日よりも上手に歩けるようになりたい、すべてにおいて、感覚的にも運動的にも認識的にも知的機能全般においても、いまできないことを絶えず次の瞬間にやろうとしているのです。グループで遊ぶ時でも、自分の出来る中で一番困難な役割を引き受けたがっている。そういう風に子どもは今できる最善の策を、最高の到達点を目指して行動しているのです。ですから子どもは絶えず発達という衝動に駆られて行動している。遊びはまさにそれなのです。私たちはこの子どもの最近接の課題にいつも集中して取り組む空間と時間を保証して行く責任があります。
次回は発達心理学の発展に大きく貢献した心理学者の一人、ヴィゴツキーが提唱した発達理論の最近接領域や外言・内言等の重要概念を紹介しようと思います。皆さんの日常の他者との関わりに役立てていただければと思います。
2023年9月1日
「心を天に向けて」Ⅱ
大宮 陸孝 牧師
「あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を引かれないようにしなさい。あなたがたは死んだのであって、あなたがたの命は、キリストと共に神の内に隠されているのです。あなたがたの命であるキリストが現れるとき、あなたがたも、キリストと共に包まれて表れるでしょう。」
コロサイの信徒への手紙3章1節~4節
教会の暦では、5月28日のペンテコステ(聖霊降臨主日)を迎え、6月4日は三位一体主日そして、その次の日曜日6月11日から聖霊降臨後主日が11月26日の聖霊降臨後第26主日まで続いて、年度の終わりとなります。ペンテコステは一年の教会生活の折り返し点です。残る年度の後半を新たな思いで進めるに当たり、初代の教会のペンテコステの出来事、聖霊の注ぎによって新たな信仰の歩みをはじめたことを覚え、生活を整え直して年度後半に臨むのです。
使徒言行録2章1節以下を読みますと、弟子たちや多くのイエスを信じて従って来た人々に聖霊が注がれ、弟子を代表するペトロが、立ち上がって説教を行った後に、その説教を聞いて受け入れ、洗礼を受けた人々が三千人ほど仲間に加わったと記されています。そして「彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと(神の恵みの分かち合い)、祈ることに熱心であった。」と記されています。人々の中に聖霊の働きが起こり、信仰が与えられて、洗礼により救いの中に生かされる人々が生まれた時、彼らは信仰者の群れの生活、教会生活をするようになりました。その教会の信仰生活の様子が43節から47節まで記されています。「信じる者たちは皆一つになって、全ての物を共有にし」という共同生活のことも記されています。
これは、厳しい迫害と同時に、国を追われるようにして、ユダヤ社会を脱出し、地中海のギリシャ地方、さらにはヨーロッパへと西の方へ移動し、生活様式を変えざるを得なかった、生活原理の大転換をしなければならなかった、そういう事情と関係があるようです。私有財産の放棄を教団が強要したわけではなく、それぞれの生活状況に従って、お互いに支え合い、励まし合う中で、自由にそのようなことが行われたということのようです。言うなれば、今の難民相互支援のようなものであったろうと思われます。
そのような日々の生活の中で、前回話しましたような、心の置き場所を地上のものではなく、上に置きなさいという勧めがなされていくわけです。今までの生活を棄てて、上にあるものを求めよと聖書は激烈なことを語りますが、その時既に人々の今までの生活は成り立たなくなっていたのです。そして民族的な移動という新しい状況の中で、今までの様々なしがらみ、自分の欲望であったり、恨みであったり、憤りであったり、貪欲であったり、悔いであったり、執着であったり、そうしたものにもはや心を置くことなど出来ない、後戻りできない状況に追い込まれていた中で、聖書は言うのです。「あなたがたは死んだのであって」と。死んだのであればもはや仕方がないのです。地上のもののしがらみから離れるほかないのです。死ねば解き放たれるのです。「あなた方は死んだ」と聖書が言う時何を言っているのでしょうか。
改めて、上記の聖句を読みますと、1節に「あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですから」とあり、3節には「あなた方は死んだのであって」と語られています。そして上にあるものつまり、「復活されたキリストと共に在るもの」を求めるのです。復活されたキリストと共にある故郷、復活されたキリストと共に在る自分、復活されたキリストと共に在る御国を求め、そこに思いと志を向ける、そこに生活原理を置く、それができるためには、この地上の罪の現実に死ぬことだ。古い自分、その人生、恨みや悔い、貪欲や怒り、憤り、地上へのあらゆる執着、それらに対して死ぬこと、そしてキリストと共に新しい命に復活させられることに基づいて初めて実現することだと、聖書は語っているのです。
「キリストと共に」というのは同時にというだけではなく、キリストの助け、力によってです。キリストの憐れみと恵みの内に古い自分に死ぬことが出来た。そして復活させられたというのです。これは同じコロサイ書2章12節にありますように、「洗礼によってキリストと共に葬られ、また、キリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられた」と言われていることです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受ける時に起こる神の救いの出来事なのです。
2023年6月1日
「心を天に向けて」Ⅰ
大宮 陸孝 牧師
「あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を引かれないようにしなさい。あなたがたは死んだのであって、あなたがたの命は、キリストと共に神の内に隠されているのです。あなたがたの命であるキリストが現れるとき、あなたがたも、キリストと共に包まれて表れるでしょう。」
コロサイの信徒への手紙3章1節~四節
4月9日にイースター(復活主日)を迎え、まもなく、5月28日にはペンテコステ(聖霊降臨主日)を迎えます。上記した聖句は、復活されたイエスに出会って喜びの内に始めた、初代教会の新しい信仰生活について記されているところです。他の人に対する態度や、家族に対する姿勢など、信仰を持って歩むキリスト教生活の根本的な姿勢について勧められているところです。
まず、「上にあるものを求めなさい」とあり、さらに繰り返して、「上にあるものに心を留め、地上のものに心を引かれないようにしなさい」と言われています。原文では簡潔に「上に思いを向けなさい」という表現です。思いを上に向けるとはどういうことでしょう。
心が疲れたときには、空を見上げて星や雲を見て、ほっと一息つきたくなる。上を向くと心が晴れやかな気分になり、癒やされた気分になる。斎藤茂吉は精神科の医者であると同時に文学方面にも関心を寄せ、数々のすぐれた作品を発表しています。その斎藤茂吉の有名な句にこんなのがあります。"最上川の 上空にして 残れるは いまだうつくしき 虹の断片"最上川の上空にかかった虹を詠んだ句です。作者が見た時には、完全な虹ではなく、消えかかり、切れて断片となっていました。その切れてしまった虹の断片の消えゆく美しさを表現しようとしたものと解釈できます。人の移ろいやすさや刹那的な人生を重ねて見ているのかも知れません。
しかし、上に記しましたコロサイの手紙では、単なる気分転換に上を向けといっているのではありません。「そこでは、キリストが神の右の座に着いておられるところ」と記されています。そしてそこからキリストが再び来られるところ、私たちも、キリストに包まれるところです。「上にあるものを求める」とは、つまり、「神の座についておられるキリストを慕い求め、キリストの御国、私たちの真の故郷を求め、キリストと共にある私たち自身の命、キリストと共にある私たちの本来の自分を求めなさい。ということを言っているのです。
この地上にある自分は本来はあの上にいなければならない存在なのだと言っています。「あなたがたの命は、キリストと共に神の内に隠されている」私たちの生活の源、命の源はそこにあるのだ。だからそこに心を置きなさいと明確に言っています。
反対に「地上のものに心を引かれないようにしなさい」とは地上のものから解放されるということです。この世に生きてある限り、私たちには地上のものがからみつきます。この後の五節には地上のものとは「情欲や悪い欲望、及び貪欲」があるといわれ、さらに八節には「怒り、憤り、悪意」といったものが挙げられております。地上のものに捉えられ、心が憤りで一杯になるそういうことも含まれると言うことです。人生で受けて来た傷もあるでしょう。自分自身の過失もあります。自分自身の悔やまれる人生もあるでしょう。しかし、心の置き場所はそうした地上のものではなく、上に心を向ける、本当の自分がキリスト共にいるまことの故郷。そこにこそ思いを向け、そこにこそ心を置きなさいというのです。この心の置き場所を変え、考えや志の向きを変え、生活の原則を転換していくことは決して容易にできることではありません。思うように生きられないままここまで来てしまった人生の悔いからどうしたら自由になれるのか。上にあるものに心を留める。どうしたらそれができるのか。このお話の先は次回にいたします。
2023年5月5日
「わたしたちは神に贖(あがな)い出された
神の家族です」
大宮 陸孝 牧師
「イエスは、「わたしの母、わたしの兄弟とはだれか」と答え、周りに座っている人々を見回して言われた。「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ。」
マルコによる福音書3章33節~35節
統一教会の問題が再浮上し、信仰と家族の問題を改めて考えさせられています。今から77年前の敗戦後「家制度」が廃止され、経済発展に伴う都市化と共に労働力を提供する若年層は農村を離れて都市部に流出し、それまで家族をまとめていた生産の場は都市の企業や工場に移り、そこで新たに夫婦を中心とした親子から成る核家族を形成し、さらに他方では高齢化が進み、老齢者のみの家族や独り暮らしの単独世帯も増え続けています。そして一般的な傾向として、離婚率が上昇し、"空の巣症候群"に陥る年配夫婦や熟年離婚も増えています。そのほか多様な家族構成へと展開して行くことになり、事実上家族がばらばらな生活となっていく傾向が強くなっています。そういうこともあってか、家庭内離婚や家庭内暴力、児童虐待など否定的な側面が表面に現れてきているように思われます。
家族の形態や構造は時代の変化と共に変わります。それと同時に家族の不変で本質的な機能とはなんなのか、愛や信頼を確保し、共に喜びを分かち合い、病気、事故、災害、そして死に際しても家族が身近な支えであり必要であるとするならば、そのシステムをどのようにして保持していくのか、家族システムのそのようなスキル形成(人格形成・教育)をどこに求めるべきなのかをしっかりと再確認することが喫緊の課題ではなかろうかと思うのです。
イエスの家族との関係を描いている福音書の箇所はそう多くはありませんが、上記の聖句はそのひとつであります。イエスの弟子たる者の道が説かれ、神のみ心を行う者こそ弟子にふさわしく、イエスの家族なのだとイエスは言われます。注目しなければならないのは、ここにイエスの家族が出てくることです。ここに描かれているイエスの家族は、イエスに対して決して好意的に関わっているのではないということです。
イエスの教えを聞こうと集まってきた群衆の対応に忙しくしているイエスを見て、「身内の者たちは」イエスが気が狂っていると思って、「取り押さえにやって来た」(21節)というのです。そしてもう一つの話しも、群衆がイエスの話しを聞いていたところへ、イエスの母と兄弟たちがやって来て、「人をやってイエスを呼ばせた」(31節)というのです。イエスの母と兄弟たち家族は教えを聞いている人々の中には入ろうとしないで、外に立ったままであったというのです。この時点ではイエスの家族は、イエスの行動とその教えには同調できない、部外者の立場を取っているのです。
イエスの父ヨセフは温厚で信仰深い人であったようであります。イエスやその他の子たちがまだ小さかった頃に亡くなったと思われます。イエスは母子家庭で青少年時代を過ごし、ナザレで農具造りの大工をしていた父、ヨセフに代わって、若くしてその仕事を受け継いで家計を助け、やもめの母を支え、兄弟姉妹たちにも気を配って面倒を見ていたのです。その生活は貧しいものであったにしても、家族は一つにまとまり助け合い、支え合って懸命に生きてきた家庭であったと思われます。それが今やイエス対母マリアと兄弟たちという対立と緊張関係がこの家に生じている。宗教的なものからこの軋轢(あつれき)が生じている。宗教上の相違から来る対立や違和感はその根が深くそう簡単には和解できるものではありません。
イエスは神に召され、やむにやまれぬ思いで立ち上がったのです。たとえ自分の母が反対しても思い直すことも後に引くこともしません。かといって自分の家族にも理解されず、受け容れられない運命でもありました。それは神に召された者の宿命的な内的苦闘でありました。けれども、イエスはご自分の家族を忘れたのでも、見捨てたのでもなく、ましてや自分の出世のために家族を踏み台にしたのでもありません。愛して止まなかった彼らへの愛は本物の愛でした。彼らとの小さな血縁の愛情を決して無にすることをしないで、自らのもっと大きな愛で、彼ら(家族)と更に全世界の人々を包み込んだのです。
十字架の贖いによって全世界の人々を救い出すことが神の御心でした。全世界の全ての人々を神の家族とするために一時源家族を離れただけのことだったのです。後にイエスの家族はそのことを理解し、重要な初代教会のメンバーとなって行きます。
2023年3月1日
「若い日にあなたの創造主を覚えよ」
大宮 陸孝 牧師
「朝種を蒔け、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれかそれとも両方なのか、わからないのだから。光は快く、太陽を見るのは楽しい。長生きし、喜びに満ちているときにも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。・・・若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。・・・知っておくがよい、神はそれらすべてについて、お前を裁きの座に連れて行かれると。心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け。・・・青春の日々こそ、お前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに。『年を重ねることに喜びはない』と言う年齢にならないうちに。」
旧約聖書コヘレト11章6節~12章2節
受験のシーズンを迎え、大勢の若者を見かけます。彼らが喜びの春を迎えることが出来ますように祈ります。昔「大学受験ラジオ講座」を聞いていました時に、単純なメロディーが三回オープニングテーマ曲として流れるのが印象深く心に残っています。この曲は、ヨハネス・ブラームス作曲の大学祝典序曲の最後4番目に出てくる曲で、今では、日本でも大学のオーケストラでよく演奏されているようです。ユニバーシアード(国際大学スポーツ連盟)が主催する総合競技大会では、開閉会式、と各競技の表彰式で、勝者を讃える歌として、この曲が演奏されます。
この曲は1267年にボローニャの司教ストラーダによって作曲され、ヨーロッパ各国に伝わる伝統的な学生歌となりました。歌詞はラテン語で、歌い出しが"ガウデアームス・イギトゥル"でこれが歌の題名にもなっています。「だから愉快にやろうじゃないか」と訳されます。歌詞は10節まである長いものですので、ヨーロッパの各大学では卒業式などには、この中の1~2節を選んで、壇上の卒業生だけではなく、フロアーの家族も、OBもOGも老いも若きも全員で総立ちになって合唱するのです。
邦訳の歌詞を2、3節紹介しましょう。
1.諸君、大いに楽しもうではないか。
私たちが若いうちに
素晴らしい青春が過ぎた後、
苦難に満ちた老後の過ぎた後、
私たちはこの大地に帰するのだから
2.私たちの人生は短い。
短くて限られている。
死はすぐにでも訪れる。
残酷にも、私たちはこの世から去らねばならない。
誰も逃れられない。
3.先に生きていた人たちは
いったいどこへ去ったというのか?
天国へ
あるいは深淵へ、彼らに会うならば行かねばならない。
この歌の背景には上記に引用した旧約聖書コヘレトの言葉があるようです。この歌は手放しで青春を謳歌する人間の自己栄化の歌ではないのです。人生を歩み出す若きエリートたちに先ず覚えてほしい。青春から老年のたそがれまで、万人が辿る人生を創造主はずっと恵みの御手の中に包んでいてくださる。その神の恵みの御手に導かれて信仰の道を歩むことこそが命を生きることなのだよ、と語りかけて来るようです。
2023年2月1日
「神の愛を心に宿して」
大宮 陸孝 牧師
「神の国は何に似ているか。何にたとえようか。それは、からし種に似ている。人がこれを取って庭に蒔くと、成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る」 ルカによる福音書13章18節~19節
あけましておめでとうございます。
新しい年の生活が始まりました。この時、私たちがまず心を向けなくてはならないのは、この世のことではなく、私たち一人一人の内なる心の動きであろうと思います。この地上での私たちの歩みは常に不条理に揺れ動いています。この世の不条理というよりも私たち自身が常に迷い続けていて、人生はすべて迷いの中にあり、絶えず矛盾に脅かされ、苦悩し続け、それらと向き合い対峙しながら、やがて、明日に向かって生きて行くために必要な、目には見えない霊の力、命の力が与えられていくということが起こっていくのではないかと思うのです。
紀元前千二百年といえば、今から三千二百年ほど前のことになりますが、エジプトで奴隷状態にありましたイスラエルの民を解放するために、神はモーセを預言者として立てます。「見よ、イスラエルの人々の叫び声が、今、わたしのもとに届いた。また、エジプト人がかれらを圧迫する有様を見た。今、行きなさい。わたしはあなたをファラオのもとに遣わす。わが民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ」(出エジプト記3章9~10節)
モーセに導かれてエジプトを脱出した民は、エジプト軍に追跡され、海辺に追い詰められ、風前の灯火となった時に、イスラエルの民は非常に怖れて主に向かって叫び、また、モーセに言います。「我々を連れ出したのは、エジプトに墓がないからですか。荒れ野で死なせるためですか。一体、なにをするためにエジプトから導き出したのですか」(出エジプト記14章10節~11節)「非常に怖れて」の絶望の声です。夢も希望もありません。やっぱりエジプトに留まっていれば良かった。どうしてこんな所へ連れて来たのか?足がすくんで一歩も前に出られません。
そして、モーセは民に言います。「怖れてはならない。落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。・・・主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。」(14章13~14節)つまり、エジプトを脱出し、約束の地パレスティナへ向かう脱出行の旅路、これはみな神様のお仕事なのだ。神様のお約束なのだ、だから神は必ず実現させるだろうという信仰がここにはあります。非常に怖れた人々のつぶやきに関係なく、「おそれてはならない」と言ったことの根拠は神の御力への信頼にあったのです。出エジプトは神に信頼し、すべてをお任せして、神のお言葉に従って行動したから出来たのだというのです。
この見えない神の約束は必ず成ると信頼して神に従い、この希望に生きること、これは私たちの人生の身近な所でも起こることでもあるのです。モーセがしたように、私たちもあせらず、気落ちせず、神の憐れみと恵みの御手を信じ、信頼し、お任せし、子供たちの成長を待つことが大切であろうと思います。もし、こどもが気落ちするようなことがあったら、慰め、励まし、見えないものへの信頼と希望をもつこと、これが私たち大人が持つべき責任であろうと思います。これは私たちすべての人間にも言えることでしょう。人の心に蒔かれた神の愛の種一粒はやがて神の力によって成長し、多くの実を結ぶのです。
2023年1月1日
*2022年のバックナンバーはこちらへ。
このページの先頭へ