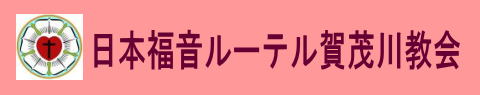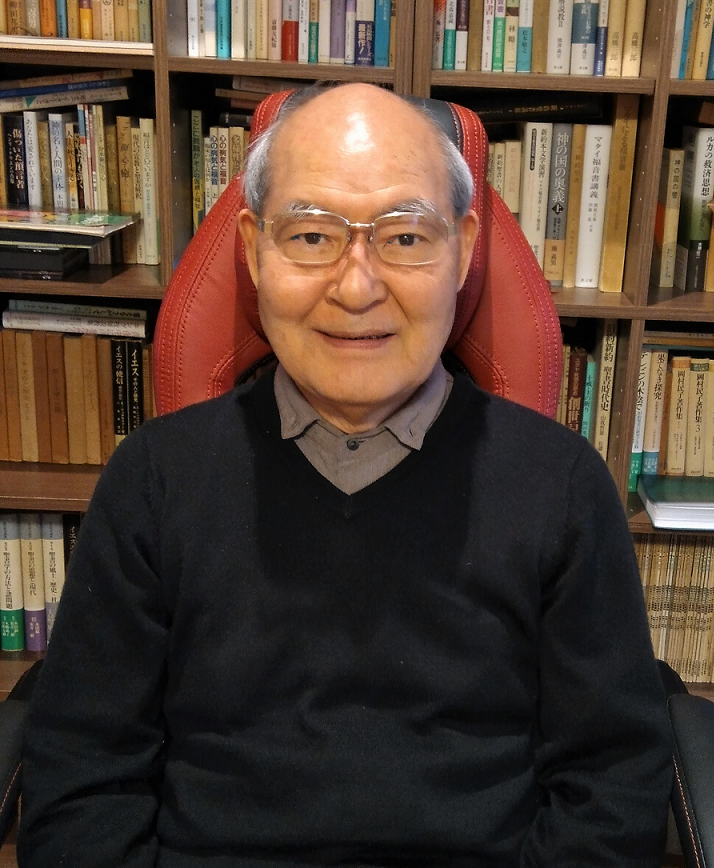牧師メッセージpastor'S message
「ひとりでいる時も大切だよ」Ⅴ
大宮 陸孝 牧師
「キリストの言葉が、あなたがたのうちに豊かに宿るようにしなさい」
新約聖書書コロサイの信徒への手紙3章16節
70数年前の日本は、敗戦の困難の中からなんとか抜け出そうと必死になって働いて復興に向けて努力し、そして、少しずつ豊かさを取り戻し、ようやく先進国の仲間入りを果たし今では、経済大国と呼ばれるようになって来ましたが、果たしてその豊かさは、私たちの人生に、毎日を生き生きと生きる真の喜びを与えていると言えるのだろうか。
冷えて行く人間関係、教師に対する不信感を持つ生徒、自分の地位を守るために相手を蹴落として行く企業内の人間関係、政治不信、社会の不正や凶悪犯罪の増加等々殺伐とした社会の現実を見るときに、こんな筈ではと思わずつぶやいてしまう現実があります。どんなに物質的に豊かな暮らしが保証されていてもそこに本当の生きる喜びはないという経験を多くの人がしています。
そして、多くの人が、人生の本当の意味、また喜びは何処にあるのかを探して、生き方を模索し始めている時代であるようにも思います。災害に遭った人、孤独なお年寄り、社会の弱い立場の人たちを進んで助けようとするボランティアの奉仕活動をする人々が増えています。これらの奉仕活動を通して、物やお金では得ることのできない素晴らしいものがあることを人々は経験しています。そして、そうした活動から改めて、親子の愛、夫婦の愛、兄弟愛等を始め、友情、働く仲間、地域コミュニティーなど、他者との関わりの内に、お金や物によっては、決して得ることのできない真の喜びがあることを体験的に感じています。
真の友は人生の宝と言われます。よい友、心から信頼できる友人に恵まれた人は幸いです。師弟や上司・部下といった上下関係でもなく、先輩と後輩の間柄でもなく、互いが対等に、お互いの人格を尊重し、尊敬し、互いに心を開いてどんなことでも話し合えるタブーのない信頼に基づいた人間関係が築ければどんなにすばらしいことでしょう。「ひとりでいる時も大切」というテーマで連続しておたよりを書いてきましたが、それは決して、「自分の中に閉じこもって、自分のことだけを考えていればいいよ」と言おうとしているのではありません。
人と人との関わりを豊かに生きるために私たちに求められる基本的な能力は何でしょうか。それは上記しました、他者の命を「尊重する」「尊敬する」「受容する」という言葉で表現することができます。一言で言うと「お互いを大切にする」「互いに愛し合う」ということです。誰もがそのようにしてお互いに仕え合い、支え合い、助け合い、励まし合い、うれしいことや心から喜べるようなことをたくさん分かち合って生きて行きたい、と思うのですが、なかなかそうはなりません。あまりやりたくないと思うことを、人から頼まれた時、素直に「はい」と言って引き受けることはとても難しいことです。たとえ自分が望まないことでも、みんなのために必要であると思えば、それを黙って引き受け実行して行くには、勇気と愛が必要です。
そのような特性を私たちがほんとうに得て、これまでとは違う新しい生き方を始めるためには、ただ単にこれまでの生き方を反省したり悔いることだけではなく、もっと根本的な生き方の転換をして行く必要があります。その克服しなければならない根本的な問題とは、私たちの人間が持つ相互の疎外と分裂です。人間の支配欲、利己主義、嫉み、不和、暴力、敵意、嘘、戦争など、私たちの現実にはこのような数え切れない罪の現実が連鎖的に広がっています。お互いの信頼関係を破るだけではなく、お互いの一致も損なってしまうその破壊力は最早人間の志しや努力の域を超えてしまって、自己回復は不可能になっています。ここで私たちは一旦沈黙しましょう。真実の癒やしの力を持つ方に聴くことにしましょう。そのために一人になって静寂の時を持ちましょう、ということです。
2024年7月1日
「ひとりでいる時も大切だよ」Ⅳ
大宮 陸孝 牧師
「キリストの言葉が、あなたがたのうちに豊かに宿るようにしなさい」
新約聖書書コロサイの信徒への手紙3章16節
3月からの主題で、今回で4回目になります。前回は大人にも一人でいることに重要な意味があること、生活をシンプルにすること、そして充実させ、豊かで意味のある人生を歩んで行くことを目指すという、シンプル・ライフについて考えましたが、その目的は全能なる神との生き生きとした新しい命の関係を取り戻すということです。私たちは神の語りかけを聞くためにまず沈黙することが必要になります。
神に祈るということは、私と神との対話であるとはよく言われることであります。私の方から神に語りかけ、いろいろ願いごとを申し上げてよいのですけれも、こちらの願いに対して神が何とお答えになるか、神が自分に何をお求めになっておられるのかを、耳を澄ましてよく聞き取るために、神の前に沈黙し、静まる必要があります。そうでなければ、祈りはこちらからの一方通行の語りかけとなり、自問自答しているだけのことになります。そこから導き出される答えは結局は自己中心的で独善的なものになってしまうでしょう。
「わたしの魂は沈黙して、ただ神に向かう。神にわたしの救いはある」(詩編62:1)静まりの時をじっくり持たないでは、神とより深く、またより親しく交わることは決してできません。この静まりの時は私たちの最も尊い経験となるでしょう。静まって神に心を向けるとは、「神と対話するために時間を取り、その時間を何よりも大切にする」ということです。じっと静まり、神の御前に耳を澄まし、御言葉を聞き取ることに心を注ぐということです。
私たちは日常の喧噪の中で、また、超過密なスケジュールの中で、心の感覚が鈍り、神の御声が聞こえなくなって、神の触れて下さる御手に対しても無感覚になってしまっているのです。そのような私たちが、ゆっくりとした時間を沈黙のうちに過ごすことは、霊的な感覚を取り戻し、憐れみの内に共にいてくださる神と、その恵みを深く深く覚える経験ができるようになる。つまり、沈黙は霊的な深まりの経験となるのです。現代の社会の中では、私たちは黙って待つことはなかなかできなくなっているのですけれども、だからこそ、沈黙の中で心を静めることは極めて重要なのです。
マザー・テレサが沈黙について次のように語っています。「私たちは神を見出す必要があります。神を騒がしく落ち着きのない所で見出すことはできません。神は静けさの友なのです。自然をご覧なさい。木や花、そして草は静かに成長して行きます。星や月や太陽をご覧なさい。なんと静かに動いているのでしょう。沈黙の祈りのうちに、多くを受ければ受けるほど、私たちの活動においてもっと多くを与えることができるのです。」
静まること沈黙することは何もしないということではありません。普段の生活の中で聞き取ることができない神の声をしっかりと受け止める時なのです。しばらく沈黙の時を持って、私たちに向けられた神の語りかけを心に刻むことができれば、豊かな心と魂の深さを取り戻すことができるのです。
2024年5月1日
「ひとりでいる時も大切だよ」Ⅲ
大宮 陸孝 牧師
「主はこう言われる。『さまざまな道に立って、眺めよ。昔からの道に問いかけてみよ。どれが、幸いに至る道か、と。その道を歩み、魂に安らぎを得よ。』」
エレミヤ書6章16節
3月からの主題で、今回で3回目になります。前回は子どもにとっての一人でいることの重要さを考えて見ました。今回は大人にも一人でいることに重要な意味があることを考えて見たいと思います。
シンプルライフとよく言われています。端的に言えば、生活をシンプルにすること、そして充実させ、豊かで意味のある人生を歩んで行くことを目指すということでしょうか。シンプルライフとはまとめてみますと以下のようになるかと思います。
1.質素で、贅沢をしない生活をすること。
2.無駄のない生活をすること。
3.1本のしっかりした筋の通った生活を送ること。
4.何が最も大切なことなのかを知って、そのことに集中して生きること。
5.満ち足りた心をもっていること。
私たちの生活に多くの浪費がないかを点検し、金銭だけではなく、時間、食事、衣服、住居、家具、旅行、余暇等において、それはどこまで必要なのかを的確に判断していく必要がある、ということです。私たちは目で見るものを欲しくなり、ついつい追い求めてしまいます。それが無くても生きていけるものに、・・・やらなくてもいいことに心を煩わせ、しなくてもよい労苦をしてはいないか。実際、心を貧しくし、飢えてくると、余計なものをたくさん買ってしまうという傾向があります。「人はパンだけで生きるのではない」とは、「パンよりももっと大切なものがある。それに心を向けよ」ということです。簡素なライフスタイルの目的は、倹約し、蓄えることが目的なのではなく、本当の意味で豊かで、満ち足りた人生を送るということです。
マタイ福音書16章24節以下で「人はたとい全世界を手に入れても決して満足することはない。今、私たちに必要なものはもっと多くのものではなく、神と共に生きることを通して〈満ち足りる心〉をもって生きることだ」と言われます。また「必要なことは多くはない。いや1つだけです。」と言われます。その一つの必要なことというのは、神との新しい豊かな命に繋がって生きるということを言っているのです。
私たちは社会の中での毎日の仕事の忙しさの中でストレスが増大し緊張しています。そして、そのストレスを解放するために、更に多くのものを求めるようになるのです。その行き着く先は行き止まりです。つまり、本当の心のケアを忘れて生活しているのです。今、私たちに必要なことは、全能なる神と命の交わりを深めるために、生活を整えていくことです。私たちにとって、今、問題となるのは、神の前に一人で立つことです。私たちが神との深く親しい交わりを持つためには、次のような決断と訓練が必要になります。
1.生活を整理しなおす決断
2.静まる決断。沈黙し黙想する決断。
3.静謐を培う(魂の静まりを培う)という決断。
4.神に信頼し、人生を明け渡し、神の言葉に信頼し導かれるという決断です。
つまり、基本的にこの四つの条件が整うのが礼拝という場なのです。
「ひとりでいる時も大切だよ」Ⅱ
大宮 陸孝 牧師
「あなたたちの父アブラハム あなたたちを産んだ母サラに目を注げ。わたしはひとりであった彼を呼び 彼を祝福して子孫を増やした。」
イザヤ書51章2節
3月のお便りの続きです。子どもが一人でいることの重要な意味を考えると言うテーマで、今回はエリーズ・ボールディングの「子どもが孤独(ひとり)でいる時間(とき)」 副題―孤独が子どもの創造性を育む―〈小泉文子訳〉を紹介します。
エリーズ・ボールディングは、ノルウェー・オスロ生まれの平和学者、社会学者で、アメリカ・ニュージャージー州在住で在りました。経済学者のケネス・E・ボールディングと結婚後5人の子どもを育てながら、平和研究に取り組み、1969年、ミシガン大学で社会学の博士号を取得、ダートマス大学の名誉教授。国際平和研究学会(IPRA)の事務局長、国際連合大学の理事などを務めました。20世紀後半の最も重要な平和運動家の独りとも言われる人物です。この名著を日本語に最初に翻訳したのが、日本の幼児教育の第一人者でもある小泉文子氏です。
否定的にしか論じられない"孤独"が実は子どもの内的成長には欠かせない必要なものであると著者は述べます。アイデンティティの認識、独創性、その他人間には一人でいる時にしか起こらないある種の内的な成長があるのだ、と著者は言います。寂しさや孤立というマイナスイメージのゆえに、子どもと結びつけて考えない孤独の、積極的な意味、"一人でいる時間"にもたらされる豊かな実りに気づかされます。
今のこどもは、内的な成長のために必要な『一人でいる時間』『自分と向かい合う時間』を確保できているだろうか。その時間は、外的世界と子どもの内なる世界とを意識的に一つに統合させ、予想も付かないような内的成長を告げる大切な時間(とき)なのだと、ボールディングは言います。この孤独は寂しい孤独なのではない。あくまで孤独(ひとり)で自らいる時間である。ケースバイケースと言うこともあろうかとは思いますが、両親やおとながスマホばかりいじっていて、子どもを一人にさせている時間は、ここで言う孤独(ひとり)ではない。それは寂しい孤独(こどく)であるということになるでしょう。
それとは対照的に、外界の世界に反応する事に多大なエネルギーを費やしていると、人間は刺激に溺れ、内面生活や、そこから生じる創造力、また、創造性の成長を阻止し、萎縮させることになるだろう、と著者は言います。その具体的な例として上げられるのがコンピューターであります。(スマホはまだ普及していなかった時代でした。)
「子どもの心は世界で最も肥沃な土地であり、知らず知らずのうちに蒔かれた種は、思いもよらない花を咲かせる」目に見えないものを洞察していくという心の動きが、人間の精神生活のあらゆる面で、どんなに重要かは言うまでもありません。後に、崇高なものを宿すかもしれない心の場所はひとりでいる時に作られて行くものだと改めて認識させられます。 以下次号
2024年4月1日
「ひとりでいる時も大切だよ」Ⅰ
大宮 陸孝 牧師
「あなたたちの父アブラハム あなたたちを産んだ母サラに目を注げ。わたしはひとりであった彼を呼び 彼を祝福して子孫を増やした。」
イザヤ書51章2節
昨年(2023年)10月に埼玉県の自民党県議団が、小学3年生以下の子どもだけで、公園で遊ばせたり留守番をさせたりすることを、子どもを放置する虐待行為とみなして禁止する、「埼玉県虐待禁止条例案を県議会に提出したところ、保護者などから「子育てをしている人の立場を理解していない」「現実的ではない」「子どもを一人で行動させることに制限をかけられるようでは日々の生活に支障をきたす」という声が多く寄せられ、この条例案は波紋を呼び、結局県議団は取り下げを決めました。
埼玉県の条例改正案に反対するオンラインサイトには、「ニユージーランドやアメリカの一部の州などでは、14歳以下の子どもだけで留守番させたり、大人の付き添いなしで公園で遊ばせたりすると「児童虐待だ」として通報されるというようなことがある。しかし、その国の治安や、チャイルドシッターの普及率の高さ、またそれに関わる金額の違い、そもそも行政サポートが圧倒的に充実しているなど、背景が日本と大きく異なっています」とあります。
福祉が充実しているドイツなどはどうなのかをさらに見てみますと、「子どもは未熟な存在」と考え、大人(保護者を含む)が監護義務を負うというのが基本的な考え方で、この監護(アウフジッヒトシュプフリッヒト)という言葉は日常生活でもよく使われているということです。「子どもが自分自身や他人に対して危険な行為をしないための責任は大人にある」という共通認識があるために、基本的に子どもが幼稚園や学校に通っている以外の時間帯については保護者が監護義務を負うということです。但し罰則規定はありません。あくまでも保護者が主体的な自覚を持って子どもを監護して行くという原則です。
同じ年齢であっても、「独りにしておくと危険な事をする傾向のある子ども」と「そうでない子ども」がいるので、その人格や成長過程によって、親が臨機応変に対応することは許されているけれども、ドイツでは「ひとりで行動する子ども」について、親に対して厳しい視線が注がれているようです。ただし、ドイツでは福祉全般で手厚い公的な支援がなされていることを見逃してはならないでしょう。
それで、私は上記したように、子どもがひとりでいる時には、大人の配慮が必要であることをふまえた上で、信仰という面においては、大人も子どもも共通して、ひとりでいることには重要な意味があるということを、二人の人の著書を紹介しつつ考えて見たいと思うのです。そのひとりはエリーズ・ボールディングの「子どもが孤独(ひとり)でいる時間(とき)」と、もうひとりはディートリッヒ・ボンヘッファーで、その著書「共に生きる生活」です。
以下次号
2024年3月1日